50年のキャリアで培った野村流「仕事のすゝめ」
クリエイティブサロン Vol.286 野村浩二氏
今回のクリエイティブサロンは、大阪で半世紀にわたって活躍してこられた野村写真事務所の野村浩二さんをお迎えし、お話を伺った。この日は後輩クリエイターをはじめ、野村さんが運営する写真教室の生徒も詰めかけ満席の状態。自ずとトークに期待が高まる中、大ベテランは飾らないフランクな調子で自らの歩みを語り始めた。
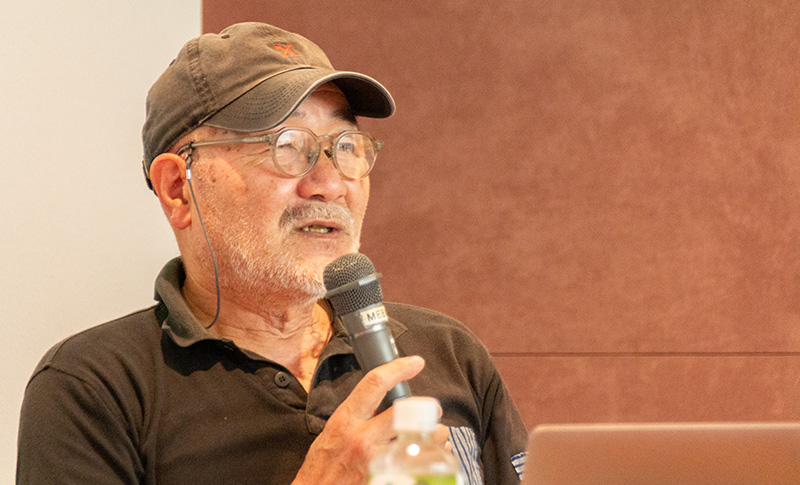
待ち受けていた地獄の3K
野村さんと写真との出合いは、高校卒業後。もともと美術に興味があったことから、一度就職して学費を貯め、日本写真専門学校(現・日本写真映像専門学校)に進学した。
ただ、学生時代はあまり勉学に身が入らず、本当の意味で写真を学んだのはむしろ就職後だそう。撮影スタジオにアルバイトとして入社し、日々実践の中で知識や技術を習得した。
ただ、当時のカメラマンは「きつい、汚い、危険」の3Kと言われた時代。撮影が立て込むと1週間スタジオに泊まり込み、機材の発泡スチロールで暖をとりながら仮眠を取ることもあったとか。月1程度しか休みがない上、安月給でボーナスがないのは当たり前。非常に過酷な下積み時代を送った。
「当時のカメラマンは職人と一緒で、10年やってようやく一人前と認めてもらえる世界でした。こんなことを言うと今の風潮に合わないでしょうが、しんどくても仕事だったら文句を言わずにする。そういう時代だったんです」
その後も野村さんは厳しい状況を物ともせず、百貨店の商材を撮影するスタジオ、ショッピングモールのチラシを扱うスタジオへ転職。次々と異分野の撮影現場に飛び込み技術の幅を広げていった。
化粧品撮影で突破口を開く
その後1983年、27歳の時に独立し野村写真事務所を設立。当初こそのんびりしていたものの、4〜5年目を迎え雑誌広告や店頭POPの撮影を請け負うようになると、下積み時代に培った実力を発揮し一気に事業を加速させた。
特に担当していた化粧品の撮影は、みずみずしく透明感ある世界を演出する一方、撮影者が映り込まないよう細心の注意を払わなければいけない、非常にテクニックの要る案件。商品撮影の中でも「難しい」とされる部類なだけに、理想通りの撮影ができると、それがクライアントからの信頼となり次々に仕事が舞い込んだ。また1997年には第15回繊研流通広告賞大賞を受賞するなど、徐々に社会的な評価を獲得していった。

当時の撮影の様子を見ると、商品に合わせて背景を作り込んだり、複雑な照明を組んで撮影したり、さまざまな工夫がなされている。なかには、本来キチッとした印象になるポジフィルムをあえてカラープリントし、ふわっとアンニュイな風合いに仕上げたものや、大判のポラロイドをそのまま印刷機にかけ一味違う雰囲気を演出したものなど、独特な表現がなされている。
「あの頃は、基本的にフィルムの時代。クライアントから『もっとフィルム以外の表現はないか?』『何か出来ることはないか?』と言われ、どうしたら応えられるか模索しながら生まれたアイデアです」
確かな撮影技術もさることながら、この豊かな表現力が野村さんのカメラマンとしての長きにわたる活躍を支えているのだろう。
名もなき植物に何を見出すか
斬新な表現の数々は、若い頃から続けている作品撮りにも見てとれる。
この日持参された野村さんの作品を見ると、フィルムで撮った写真をあえて火で炙り、その様子を撮影したり、砂で丸みをおびたフォルムを描いてお尻に見立てたり、また2本のスプーンの先に糸をかけて上から吊るし人が支え合う姿を表わしたりと、実に自由な発想で撮られている。
野村さんが一番大切にしているのは、オリジナリティーを出すこと。自分の視点を見つけることだと言う。ただそれは、お金や人の手をかけ特殊な世界を作りこむこととは少し違うようだ。
「私はどちらかと言うと、山で摘んできた名前も知らない植物とか、海岸に打ち上げられて干からびた海藻なんかを撮るのが好きです。そういう日常に転がっているよく分からないものをどう捉え、どう表現するか。そこに撮り手のオリジナリティーが出ると思うんです」
今年も5〜6月に行われた「Osaka Art & Design 2024」に出展し、梅田大丸店の一角で写真展示を行ったそう。来年以降の出展にも意欲を見せる。

大変革期をサバイブする
サロンの中盤になると、話題は関西のクリエイティブ業界が抱える問題点へ。一般的に、東京に比べて低予算と言われる関西は、技術と経験を持ち合わせた一人前のカメラマンでも驚くほど安価な金額を提示されることがある。写真の二次使用に関しても追加費用が支払われないことが多く、仮に費用を請求しても「そんなことしたら次から仕事が来なくなるよ」と一蹴されてしまう。本来、東京のようにプロダクションが介在すれば、クリエイターに代わって交渉してくれるのだが、残念ながら関西ではあまり機能していないのが実情だ。
さらに近年は、社会全体が「ある程度のレベルで安く収めたい」という風潮になり「もっと良くしよう」という意識が弱まっていることにも不安の念を抱いていると語った。
また終盤を迎え質疑応答の時間になると、フィルムカメラからデジタルカメラへの移行について質問が寄せられた。1981年のデジタルカメラ登場以降、カメラ業界では大変革期を迎え、それに伴い野村さんも自然とフィルムカメラから移行したそう。現在はほぼデジタルカメラを使っていると言う。
当時のことを振り返り、「詳しいことは、雇っていた若いカメラマンから教わりました。やっぱり彼らの方がデジタルに長けていますから。おかげで一時期は立場が逆転し、彼らがチーフカメラマン、僕がセカンドやサードに回ったこともありました」と笑う。大変革期ゆえの苦労話を予想したが、野村さんにとってはさほど大きな問題ではなかったようだ。
そこでサロン終了後、フィルムとデジタルの使い分けについて質問してみると「特にない」という答えが返ってきた。野村さん曰く「被写体が面白ければ機材はどちらでも一緒。アイデアが面白ければ、自ずと写真は面白くなるものです」。
たしかにカメラ機材は重要な相棒だが、あくまで手段であり目的ではない。要は被写体をどう捉え、どう表現するか。昭和から令和にかけ価値観が変容し、機材も進化する中、野村さんは一貫してそのアイデアを追求し続けている。
ChatGPTをはじめとするAIの登場により、社会の有り様が変わりつつある現在。クリエイティブ業界においてもさまざまな転換が求められている。時代の流れに翻弄されず、何を目指し何にこだわるか。大ベテランのこの姿勢は、我々後輩クリエイターが明日を探る上で大きなヒントとなるのではないだろうか。

イベント概要
フィルムからデジタルへ カメラマンとしての半世紀のあゆみ
クリエイティブサロン Vol.286 野村浩二氏
1974年にカメラと出会ってから50年が過ぎました。これまで企業広告の撮影を中心にあらゆるモノや人を撮影してきました。カメラマンとしてのキャリアをスタートした当時はフィルム、現在はデジタルと大きな変化がありました。「大阪で一番暇なスタジオ」を運営しながら、時代の変化にどのように対応してきたのかなどをお話しします。また、個人的な作品や写真教室など、現在そして未来に向けた活動についてもご紹介します。
開催日:
野村浩二氏(のむら こうじ)
野村写真事務所
カメラマン
1954年高知県生まれ。1977年に写真学校を卒業、大阪市内のスタジオで実績を積んだ後、1983年に野村写真事務所として独立。大手企業の商品、人物、企業イメージなどの撮影を手掛ける。1997年に第15回繊研流通広告賞大賞受賞など賞多数。企業広告の撮影と並行して個人的な作品制作にも取り組む。写真教室「空スタジオ」では、アマチュアから新人カメラマンまでを対象にレッスンも行っている。

公開:
取材・文:竹田亮子氏
*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。
