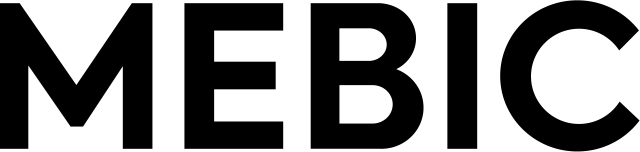メビック発のコラボレーション事例の紹介
現実を超えた可能性を、仮想空間に求めて
メタバースによる資料室と展示会の制作
勉強会から生まれたクリエイティブチーム「メタつく~る」
数年前からよく耳にするようになった「メタバース」。インターネット上に構築された仮想空間のことで、ユーザーはアバターというキャラクターの姿となって交流や活動を行う。以前から、このメタバースに興味を持っていたのが、広告制作を生業とするクリエイター、HARIKI ind.の榛木富三さん。2022年頃、クリエイター仲間の薦めで、最新のVRゴーグルを体験し「これはすごい! 明日にも購入しなければ!」と感動。その勢いに乗ってメタバースを楽しむ集い「夜な夜なメタバースの会」を開始した。
コロナ禍を経た2023年頃、会の参加者を増やそうと思った榛木さんたち。メビックが主催する交流会「Mebic Talk-in」でクリエイターに声をかけ始め、2023年秋に集まった仲間でメタバースの勉強会「メタバースの未来を語り合う会」を発足。月1回のペースで開催し、学びと交流を深め始めた。「会を続ける中でメタバースの案件を受注して、マネタイズしていこう!という機運が高まりました」と榛木さん。メンバーによる営業活動が始まった。
「本業の印刷業とは別に、地域活動を通じて地元の柏原市にある『亀の瀬地すべり歴史資料室』のリニューアルを知ったんです」と語るのは、メンバーの一人である古賀印刷株式会社の竹田保さん。同室は、地域に被害をもたらしてきた地すべりを防ぐために、古くから取り組まれて来た対策工事などを紹介する資料館だ。「当時、偶然にも資料室の建て直しがあり、稼働していたARコンテンツも更新するタイミングと聞いて、更新業務を受注した業者にメタバースを提案しました」と、待望のメタバース制作を担当することになった。
制作にあたって、竹田さんと榛木さんは勉強会メンバーのクリエイター二人に声を掛けた。一人目が、映像制作をメインに活動する今西優太さんで、3DCGの経験があり、独学でプログラミングも学んでいた。二人目が、勉強会の講師も担当していた坂野愛子さん。イラストレーターとして活動しながら、専門学校で3DCGを教えていた。計4名でメタバース制作チーム「メタつく~る」を結成することになったが、「全員が初めてのフルスクラッチでのメタバース制作。“分からないところが分からない状態”からのスタートでした」と坂野さんが言うように、手探りのプロジェクトが始動した。

トラブル続きのメタバース制作
メタバース制作にあたってメンバーの役割を分担。竹田さんはクライアントである河川事務所との窓口業務の他に、全体ディレクションと一部のグラフィックを。榛木さんは、プロダクトマネージャーとして、何を、どんな作り方で、どう作るのか?という、具体的な制作方法の指示や仕様を決める役割を。この二人を指揮官としながら、今西さんと坂野さんが3Dモデリングを担当。最終的には、今西さんが『Unity』というゲーム開発エンジンに各種データを統合してアップロードすることになった。
制作開始は2024年11月。制作するのは、新たに建てられた展示室を再現したものと、周囲のランドスケープなど。竹田さんは「メタバースではあるものの実際の建物があるため、そのサイズに合わせたいという要望がありました」と言い、そこで活躍したのが、坂野さんの”図面を読む”スキル。「以前、建築関連の職場で勤務していたんです。図面を見ながら、実寸法で展示室の3Dモデルを作っていきました。難しかったのが、展示室を繋ぐアーチ状の通路。図面に細かな寸法が書かれておらず、図面をトレースしながら、どの角度から見ても違和感がないようにしました」。
また、違った側面の課題として挙がったのが”データ問題”。各自の環境で制作したデータを統合する役割だった今西さんは、「初のチームでのメタバース制作だったので、データ共有のノウハウがない状態。データの受け渡しをミスして、データが上書きされるトラブルが起こってしまったり……。データ管理が難しかったですね」と語る。他にも、坂野さんが『Blender』というソフトで作った3Dモデルを、今西さんが『Unity』にインポートした際に色が大きく変わってしまい、何度も調整しなければいけないことも。
「制作中は、ほんまにできるんかな?と毎日ヒリヒリしてました」と笑う榛木さんだが、制作、検証、修正の試行錯誤を繰り返しながらも、一歩ずつ、着実にプロジェクトは進行。展示室をはじめ、周囲の芝生や木々などのランドスケープも完成。竹田さんが制作した展示室内のパネル展示のグラフィックデザインも仮想空間内へ貼り込まれ、全ての作業が完了した。

メタバースの表現力を駆使して地下空間も見える化!
2025年3月、「亀の瀬地すべり歴史資料室」のウェブサイト内にて、完成したメタバースが遂に公開された。木立が囲む芝生の広場に立つ3棟の展示室。中に入ると地すべりに関する歴史や土木技術が、多くの展示パネルによって紹介されている。屋外のあるポイントの上に立つと、落とし穴に落下するようにして、巨大な柱が林立する広大な地下空間へ。実はこの柱は、地すべりを食い止めるために打たれたコンクリート製の杭で、メタバースならではの表現も盛り込まれている。
完成したメタバースについて、大和川河川事務所の堀川裕太さんは、「メタバースの取り組みは『過去と未来をつなぐ、知と技術の架け橋』のような存在になると感じています。現地を訪れなくても仮想空間でリアルに現地を体験できるほか、現地では見ることができない地層や杭の構造も仮想空間では見ることができます。地すべりという馴染みのないテーマを直感的に、かつ没入感をもって体験できるのは、まさに未来型の学びだと考えており、防災だけでなく、歴史的な背景も踏まえた教育や観光、地域づくりなど、さまざまな分野と連携した更なる進化に心から期待しています」と語り、プロジェクトは成功を収めることができた。

「メタつく~る」は、実はこのプロジェクトの他に、「IT系企業4社合同のメタバース展示場」という、メタバース制作も行っている。「亀の瀬と同じ体制で取り組みましたが、ノウハウが蓄積できていたのでスピーディーに完成しました」と榛木さん。制作期間は約1ヶ月半で、2025年2月に制作を開始し、4月には公開。メンバーのスキルも着実に向上している。
クライアントである株式会社エステックの松倉崇志さんは、「ネットワークの課題解決に強みのある4社でメタバース展示会を開催しました。来場者のコミュニケーションを活性化させるために、広場を中心にして各社の展示場を配置。テキストや音声で、気軽に接客や商談ができるよう提案&制作いただきました。このメタバース展示会で4社のシナジーが得られればと思っています」と語る。来るべくメタバース時代をにらみながら、一歩先行くビジネスチャンス創出を期待している。

「メタつく~る」が次に見すえる山の向こう
メタバースに挑んだ「メタつく~る」。プロジェクトを振り返ってみて、4人のクリエイターは何を思うのだろうか?
坂野さんは「全員が初挑戦のなかで完成させられたことに、大きな達成感がありました。新しいスキルを習得することもできたし、今後も学んでいきたいです」と充実感をにじませる。
続いて竹田さんは「印刷という本業が減っているなかですが、メタバース空間では展示パネルのようにグラフィックデザインを活かす余地もある。実績もできたし、営業ツールとして活用していきたいと思います」と、大きな手応えを感じている。
今西さんは、「仕事で繋がったのではなく、友達のような繋がりから始まったメンバー。フラットな関係性が新鮮だったし、ストレスなく取り組めた理由。そんな仕事の在り方を知れたのが一番の収穫だと思います」と、信頼関係の上に成り立つ仕事に魅力を感じたという。
榛木さんは「異分野のクリエイターが集まって、一つの成果を出せたことに意義を感じています。メビックが無ければ実現できていないし、本当にいい人たちと巡り合えました」と総括する。
初の挑戦で大きな成果と手応えを手にした「メタつく~る」。今後、何をめざして活動するのだろうか?「次の目標はゲーミフィケーション。メタバース内で会社のガバナンスを学ぶなど、メタバースとゲーム要素を組み合わせたビジネスコンテンツを実現したいと考えてます。それが次にめざす山。そこに向かうためには、このメンバーの力が必要不可欠」と、榛木さんは未来を描いている。
メタバースの語源は、「meta(超)」と「universe(宇宙)」。信頼関係を原動力に、それぞれが新たな挑戦に向き合い、たどり着いた世界。次はどんな景色が見えるのだろうか。それはもはや宇宙規模? 想像もおよばない「メタつく~る」の飛躍に“超”期待。
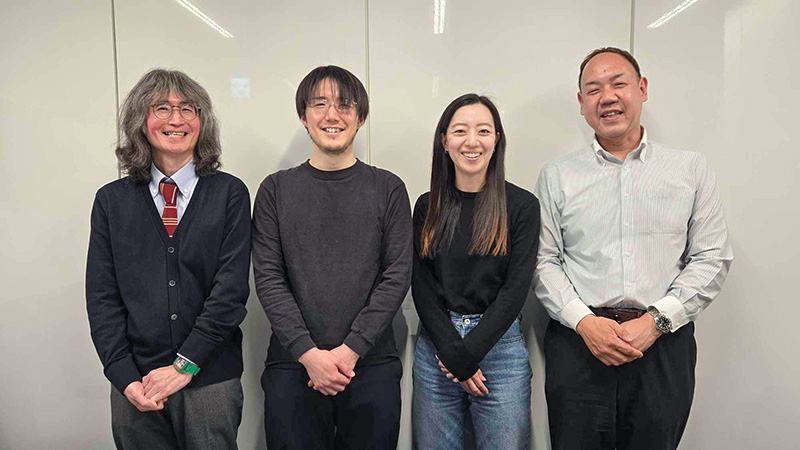
古賀印刷株式会社
メタバース・XR事業部
竹田保氏
映像クリエイター
今西優太氏
aicopan
イラストレーター
坂野愛子氏
HARIKI ind.
メタバースエバンジェリスト
榛木富三氏
公開:2025年6月5日(木)
取材・文:眞田健吾氏(Studio amu)
*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。