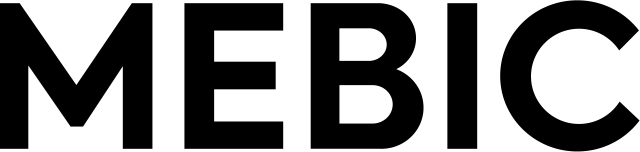メビック発のコラボレーション事例の紹介
知られざる職人技をブランド化し、全国へ
大阪かばん「ANJOER」誕生

ブランドの確立をめざし、試行錯誤を続けた日々
大阪は知る人ぞ知る、かばんの産地だ。その歴史はおよそ130年にもおよび、革製かばんを中心に様々な種類のかばんを生産するメーカーや、材料を扱う商社などが集積している。しかし、産地としての知名度は兵庫県・豊岡におよばない。上質なものづくりを行っているのに、このままでは次の世代にバトンを渡せないかもしれない……。そんな不安ともどかしさを感じ、打開策を模索していたのが大阪かばんブランド委員会だ。
「メンバーは大阪でかばん会社を営む若手経営者が中心です。大阪でかばんを作っていることをもっと知ってもらいたい、そのために『大阪かばん』というブランドを作ろうという思いで組織を立ち上げました。7年ほど前のことです」
そう語るのは、同委員会で委員長を務める株式会社シノダの篠田英志さん。篠田さんをはじめ、メンバーの多くはかばん職人であり経営者ではあるが、ブランド作りに関してはまったくの素人。組織の立ち上げ当初は講師を招き、「ブランドとは?」などの勉強会を行っていた。扱う革を統一したうえで、メンバー各社が独自商品を開発したこともあった。トートバッグなど、アイテムを一本化したうえで各社がオリジナルデザインで商品を作るというチャレンジも行った。
「でも、どれも期待したような成果には至りませんでした。メーカーの枠を超えたブランドとしての統一感が、なかなか出せなかったのです。統一感のなさは、接客のときのトークにもストーリー性を持たせることができない、それゆえお客様の心をつかみにくいという弊害も生んでいました」
このような試行錯誤の時間を経てたどり着いたのが、「ブランドとしてシリーズ物の商品を開発しよう。そのためには、ブランドの統一されたコンセプトを定めよう」という考え。とはいえ、それができる人材はメンバー内にはいない。そこで社外のプロの力を借りるべく、メビックの門を叩くことにした。

カギとなるコンセプトは「隠れた美学」
委員会がメビックを最初に訪れたのは2024年6月。課題や要望を伝えたところ、ほどなくクリエイターとの話し合いの場であるクリエイティブクラスターミーティングが開催された。
ミーティングに参加した10人のクリエイターを前にして篠田さんは、これまでの取り組みを説明するとともに、「メンバー各社はそれぞれに素晴らしい技術を持っている。欠けているのは各社をまとめるための核となるもの、すなわちブランドのコンセプトだ」と伝えた。
ミーティング後は、メビックならではの飲み会を開催。よりフランクな雰囲気のなか、委員会の思いやクリエイターそれぞれの得意分野などについて情報交換を行った。その結果、委員会はともにプロダクトデザイナーである鹿野峻さんと南大成さんに協力を依頼。現在に至るチームが結成された。
チーム結成時の心境を「課題が非常に明確で、デザイナーにとってやりがいのあるプロジェクトだと感じました。地元・大阪のものづくりに貢献できることも魅力でした」と語る鹿野さんは、プロジェクトの始動にあたってまず、南さんとともにメンバー各社の工場を訪ねて回った。そこで各社が持つ独自の技術やかばんづくりにかける思いなどをヒアリング。コンセプトの種となるキーワードを集めていった。

「みなさんのお話からは、ステッチの細かさや裏打ちの仕方、小口の美しさなど、表からは見えないような細部にこだわりと高い技術が詰め込まれていることがわかりました。それを私と南さんは『隠れた美学』と表現し、コンセプトに据えました」(鹿野さん)
南さんは、「革製のかばんは決して安価な商品ではありません。だからこそ、戦略も大切です」と語る。
「価格に見合う価値があると納得してもらう必要があるのです。そのためのキーワードの1つが『所作』です。かばんを開きやすい、中のものを取り出しやすいなど、美しい所作を実現するかばんをめざしました。これを実現するには高度な技術が必要です。高い機能性を持ちながらも、あくまでもシンプルで日常に溶け込みやすいデザインを追求しています。これもまた、優れた技術力なしには不可能です。めざしたのは、大阪かばんだからこそ作ることができる、価格に見合った価値のあるかばんです」(南さん)
デザイナー陣の提案を、篠田さんは「自分たちにはない新しい発想」として受け取った。メーカーであるメンバー各社は、「自分たちはあくまでも黒子。主人公は販売店」という意識があったという。まして多くのメンバーはOEM生産に軸足を置いており、自社ブランドを前面に打ち出してきた経験は少なかった。いわば、隠れていることこそが本来の自分たちの姿だと認識していたのだ。
「隠れていたものを表に出そうなんて逆転の発想ですよね。でも、黒子である自分たちは、今まさにオリジナルブランドを作って表に出ようとしているのです。そういう私たち自身の状況にマッチしているようにも思え、とても気に入りました」(篠田さん)
メンバー各社も同様の感想を抱いたという。こうして、「隠れた美学」というコンセプトのもとで各社の商品づくりが始まった。

互いへのリスペクトが有意義なコラボを実現する
チームがめざしたのは、2025年2月に東京で開催されるギフトショーでの新ブランドのお披露目。メンバー各社が1アイテムずつ新商品を作ることになった。デザイナーから提示されたデザイン案を見たとき、あるメンバーは「どえらいのが来たと思った」と打ち明ける。何度も型紙を描き直し、デザインを実現する作り方を探っていた。他のメンバーも多かれ少なかれ、同じような経験をした。
「できないことを『してください』と言うデザイナーさんもいます。それは無茶な話です。でもお二人は、『作りやすいように変えてくれていいです』と言ってくれました。こう言われると、信頼されていることがわかってがぜん、やる気になるのが私たち職人です」と振り返るのは、株式会社西川商店の西川晃正さん。鹿野さんも、「デザイン通りに作ってもらうことではなく、各社の強みや特徴が引き出されたかばんを作ってもらうことを目標にしていました。ですから、変更は何の問題もありませんでした」と言う。また、難しそうだからといってすぐにあきらめないのが職人の職人たるゆえん。「こうすればできる」というデザイナーへの逆提案や、メンバー同士が集まって「この方法ならできるのでは?」とアイデアの交換も行われるようになった。
こうして迎えたギフトショーでは、南さんと鹿野さんが提案したブランド名「ANJOER(アンジョア)」のもと、7つのアイテムが勢ぞろい。統一感ある7つのかばんと、さらにブランドコンセプトを反映したブースが、多くの来場者の関心を引き付けた。
「私たちもそれまでに展示会やポップアップストアなどに出てきましたが、ブースの作り方がまったく違いました。コンセプトに基づいた商品の見せ方やグラフィック、ブースの全体像など、『さすがはデザイナーさん』とうなるばかりでした」(篠田さん)

ANJOERは6月3日から、アイテムを絞ってクラウドファンディングでの先行販売が始まった。12月には全アイテムを携え、ポップアップストアでの一般販売とオンラインショップの開設を予定している。いよいよ、消費者のもとに商品が届くフェーズがスタートするのだ。
ここまでの足取りを振り返って篠田さんは、「ものづくりについては、メンバー各社はプロフェッショナルです。そこに、コンセプトという横ぐしを刺してもらうことで新しい大きな力が生まれました。クリエイターとのコラボの威力を実感しています。デザイナーと職人とが互いをリスペクトして信頼関係を築けたことが、有意義なコラボを実現するカギになりました」と語る。
「OEMでは、自分が作った商品に自分で値段をつけることができません。でもANJOERでは、それができます。どんなものを作って、どこに持って行って、誰に対して、いくらで売るか。それを考えられることが楽しいです」と語るのは西川さん。その力強い言葉は、次なる展開を見つめるメンバー全員の気持ちを代弁しているかのようだ。

下段左から、鹿野氏、篠田氏、南氏
大阪かばんブランド委員会
委員長 / 株式会社シノダ
篠田英志氏
株式会社生田 代表取締役
長井宏治氏
株式会社葛西 代表取締役社長
葛西範久氏
株式会社クロスライン 代表取締役
辻野孝太郎氏
株式会社曽我部 代表取締役
曽我部孝徳氏
株式会社西川商店 代表取締役
西川晃正氏
横武株式会社 代表取締役
松本充弘氏
株式会社ヨシカワ 代表
吉川哲司氏
合同会社アルルカンプロダクト
プロダクトデザイナー
南 大成氏
matataki design
プロダクトデザイナー
鹿野 峻氏
公開:2025年6月2日(月)
取材・文:松本守永氏(ウィルベリーズ)
*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。