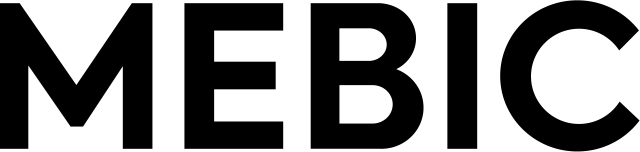何かとつまずきの多い人生も「動けば、変わる」
クリエイティブサロン Vol.306 シガマサヒコ氏
どっぷりハマったアマチュア演劇の世界から、「普通」の社会への復帰を試み、やがてフリーランスの編集者&ライターへ。ドラマチックな人生のキーワードに掲げたのが、「つまずき」と「きづき」。最後の「きづき」として挙げた「動けば、変わる」の言葉が、現在に至るまでのシガマサヒコさんの葛藤を象徴していた。

生後すぐ死の淵に立ち、高校進学で絶望を味わう
最初のドラマは生まれてすぐ。生後1か月で髄膜炎になり、「生存は難しい」と医師から告げられた。両親ともに音楽関係の仕事に就いており、当時はドイツ暮らし。実は母親が日本に帰省した際に、予定外の出産でシガさんは生まれたのだ。重篤な我が子を抱えて身動きがとれないなか、父から呼び戻される形でドイツへ。図らずもこれが功を奏し、ドイツでの投薬が運よく効いて九死に一生を得た。
帰国後、5歳のとき再び髄膜炎を発症するも、なんとか克服。両親は離婚し、休みなく働く母の背中を見て育ったそう。そのころ母と一緒によくテレビで映画鑑賞をしていたことが、のちの映画好きや演劇好きのきっかけになった。
夢中になって勉強し、成績が急上昇した中学時代とは一転し、「暗黒期」と話すのが高校時代。志望校があったにもかかわらず、塾の先生に勧められるまま別の高校を選んでしまった。「人生初のつまずき。きちんと調べなかった自分が悪いのですが、当時の自分が行きたかった自由な校風の公立校とはまったく異なる、非常に校則の厳しい男子校でした」とシガさん。やる気をなくして成績は急降下し、3年生時にはクラスで最下位まで転落していた。
当時のささやかな楽しみが読書。司馬遼太郎、志賀直哉、江戸川乱歩などの作品を好み、素人ながらも小説や漫才の台本など「書く」ことへの興味を持ち始めた。その後1年間の浪人生活を経て関西大学に入学し、住み慣れた名古屋から大阪へ。

演劇に光明を見出し、社会の呪縛から解き放たれる
「大学へ行けば天国のような楽しい毎日が待っているはず」。淡い期待はすぐに消えた。「授業はつまらないし、映画サークルに入ったもののなぜか面白さを感じることができず脱退。なんか違うぞと思いました。気づいたのは、手段と目的の混同。大学へ行くことは何かの手段であるべきなのに、僕は大学合格自体が目的になっていたため、方向を見失っていたんです」。2年生の後半からは大学へ行かなくなり、「普通」の社会で働くことに自信を失っていた。
虚無感に襲われる日々を過ごしながらも、「いつか映画を撮りたい」と秘かに書き続けていたのが映画の脚本。映画雑誌などに掲載された脚本を参考に創作した。友人からの勧めで三谷幸喜原作・脚本の演劇『笑(わらい)の大学』を観たのは、ちょうどそのころ。内容の面白さや手法に衝撃を受けて「これだ」と確信し、演劇の脚本づくりへと舵を切った。
「1本書き上げてみると、自分の手で上演したいと思うようになったんです。でも劇団の作り方はもちろん、小劇場の世界のことも当然、何も知りません」。まずは準備段階として役者の経験を積もうと社会人劇団に入団。大学は退学するつもりだったが、母の猛反対を受けて1年間の休学ということで決着した。
そこはまさに別世界だった。「自分はダメな人間だと思っていたけど、のちに一緒に劇団を旗揚げする相棒は一浪して入った大阪大学を数か月で退学しているなど、自分と似た価値観の人ばかり。なんて居心地がいいんだろう」
復学して無事に卒業すると念願の自劇団を創設。学習塾の講師や新聞社でのアルバイトなどで生計を立てながら「少人数の会話劇」にこだわった脚本・演出を手がけ、5年間で7公演を実施した。「ジャンルは喜劇。少しずつ狙ったところで笑いがとれるようになり、作品が受け入れられる喜びと、ものづくりにおける試行錯誤の大切さを実感しました」

「普通」の社会へ戻り、編集・ライターとして悪戦苦闘
終幕は突然だった。一緒に劇団を支えてきた相棒が「結婚するから退団したい」と伝えてきた。演劇活動を続けることも考えたが、「ここが引き際」と引退を決意したという。
課題は「普通」の社会への復帰。「正社員経験なしの28歳。できることといえば脚本を書くことぐらいで、ライターの道しか思い浮かびませんでした。でも、当時はライター未経験者の採用なんてありません」。ようやく見つけたのが教材制作会社のアルバイト。編集部に所属するとともに、宣伝会議の「編集・ライター養成講座」で基礎を学んだ。
努力が実を結び、出版社に正社員として入社。編集者・ライターとしての一歩を踏み出すと、大きな壁が待っていた。「脚本で使う口語体に対し、企業の紙媒体は文語体が基本。適切な日本語も求められます。原稿には上司から1文字残らず修正の赤字が入れられ、遠くから見ると赤い紙のよう」。プレッシャーに加えて「人の倍以上の作業をこなして追いつこう」と無理したこともたたり、急性胃腸炎や心因性腰痛に悩まされるが、なんとか一定のスキルを身につけ、キャリアアップのため転職を決めた。
次に入社したのはデザイン会社。「ここにも偉大な先輩がいて再び修正の嵐でした」という半面、徐々に修正は減り、2年目には信頼を得るまでになった。このころに結婚し、家族との時間や健康を重視するようになり、働き方や制作への考え方に疑問を感じ始めたそう。やがてストレスで体調不良が常態化し、妻から心療内科の受診を勧められるほどに。「そんなとき近親者が白血病になったことで、人生の残りの時間を意識するようになったんです。このままでいいのか? 何かを変えた方がいいのか? 考えがまとまらないまま、勢いで転職してしまいました」
結果的に判断は裏目に出た。規律の厳しい社風が合わず、うつを発症して4か月で退職。それでもまだ転職サイトを調べる姿を見かねた妻から「もう働かんでええから、春まで公園で太陽浴びとき」と諭される。とはいえ家族を抱える身としては「わかりました」というわけにもいかず行動を起こす。

素晴らしき哉、フリーランス!
とりあえず仕事のことは置いておき、まずは体調面の問題から解決しようと訪ねたのが、前に勤めていたデザイン会社の先輩。「その先輩は心療内科系の治療に詳しかったので、アドバイスを受けるためでした」と、シガさんは振り返る。帰り際に「暇なので何か仕事があれば」と伝えたところ、「ちょうどいい案件がある」と仕事を紹介され、すぐに別の先輩からも多くの依頼が寄せられた。最初に入社した出版社にも新年のあいさつのメールを送り、現状も伝えたところ、かつて厳しく指導してくれた上司から「仕事ならいくらでもあるよ」とありがたい言葉。こうして半ば成り行きでフリーランスでの活動が始まる。
「ひとりで過ごす気楽さ、ひとりで決められる納得感は、本当に自分にフィット。もっと早くなればよかったと思うほどです。改めて感じるのは『動けば、変わる』ということ。演劇の世界に飛び込むことも、フリーランスになることも勇気がいるけど、腹をくくればなんとかなるもんだなと」。目標は「上より前へ」。高いところをめざすよりも、長く実績を重ね続けることに主眼を置く。
とくにデジタル化が進む今だからこそ、パンフレットづくりで困っている人を助けたいとの思いが強い。また、紙媒体の魅力を伝えるため始めた取り組みが、親子向けパンフレット制作ワークショップ。「パンフレットを作り終えた親子から『ありがとう。楽しかった』と言っていただいたときには、うれしくて涙が出そうでした。演劇で笑ってもらえたときの喜びと共通するものがあります」
急性胃腸炎を繰り返した結果、今では慢性胃炎に。さらに、フリーランスになりデスクワークの時間が増えたことでヘルニアも発症。「人生はつまずきばかり」と嘆くシガさんだが、その表情は楽しそうだった。
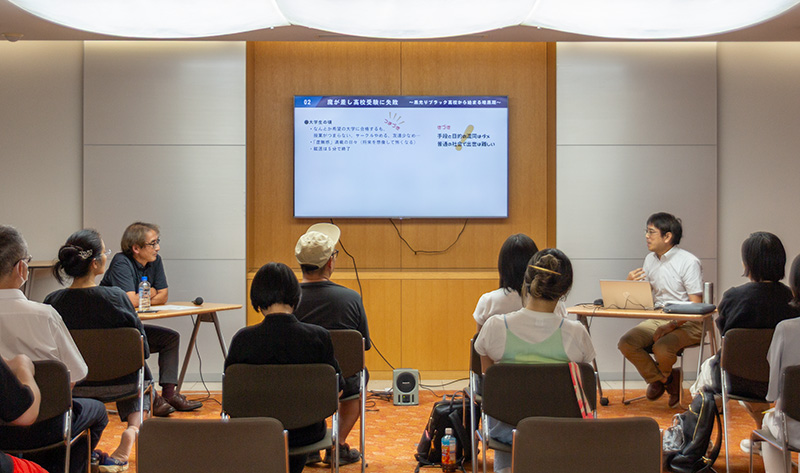
イベント概要
「つまずき」から得た「きづき」。演劇とフリーランスの世界で学んだこと
クリエイティブサロン Vol.306 シガマサヒコ氏
一浪までして入った大学生活に違和感を覚え、演劇の道へ。平穏に会社員人生を送るつもりだったものの限界を感じ、フリーランスに。「つまずき」から入ったふたつの世界は、自由でシビアで、どこか居心地がよくて、似ているところがあるように思います。編集者・ライターとして、なんとか20年続けてきたこれまでの足どりや、今後チャレンジしていきたい取り組みなどとともに、演劇とフリーランスの世界で学んだことについて、お話しさせていただきます。
開催日:
シガ マサヒコ氏
eパンフLab
ライター / 編集者
1977年、愛知県名古屋市出身。大学進学を機に大阪に出てきて以来、吹田に住みつきほぼ30年。これまで出版社や教材制作会社、編集プロダクション、デザイン会社などで、編集者・ライターとしてキャリアを積んできました。「わかりやすい、には価値がある」をモットーに、広報誌や会社案内パンフレット、社内報、記念史などの広報ツールを中心に、インタビューライティングやWebライティングにも対応。そのほか、パンフレットづくりが体験できる親子向けワークショップ「ハッピーパンフレットラボ」の企画・運営も手がけています。

公開:
取材・文:笹木博幸氏(OFFICE PIYO)
*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。