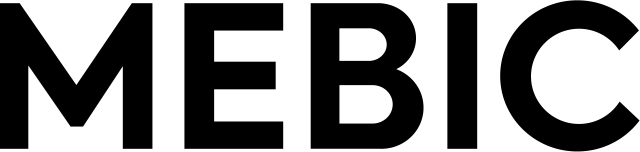ふたつのタイプから考えるこれからのクリエイターのあり方 Vol.2
クリエイティブクラスターフォーラム OSAKA UNDER40 CREATORS
20代で身につけた経験や人生哲学をもとに、クリエイターとして生き方の足場を固める30代。唯一無二のスキルで頭角を現すスペシャリストタイプになるか。ヒト・モノ・コトをつないで新たな価値を生み出すプロデューサータイプになるのか。
メビック扇町は2016年2月、大阪で活躍中の40歳以下のクリエイターたちが体現する2つの生き方にフォーカスし、これからのクリエイティブシーン活性化のヒントを探すインタビュー冊子「OSAKA UNDER40 CREATORS」を制作。当フォーラムでは、冊子に登場したメンバーのリアルなトークに耳を傾け、彼らの思考と熱を共有する。

この日のゲストはデザイン会社を率いるディレクターや、イラストレーター、プロダクトデザイナー、庭師からなる5組6名。当代注目のクリエイターたちが、異種格闘技よろしく、時に真剣に、時に笑いを交えて繰り広げた言葉のライブセッションからは、冊子に掲載された数ヶ月~1年前のインタビュー内容すら過去のものに感じられるほど、さらに進化した彼らの「今」が浮き彫りになった。
パネリスト

デザインとアートをつなぎ、生活者へ届ける「橋渡し役」 池田敦氏
G_GRAPHICS.INC
クリエイティブディレクター / プロデューサータイプ
今勉強したいことは「英語」。

クリエイティブを解き放ち、未来を照らす実験開拓精神
大垣ガク氏
アシタノシカク株式会社
アートディレクター / プロデューサータイプ
最近「古事記」にハマり中とか。

造園界にクリエイティブな風を起こすニューウェイヴ
辰己耕造氏・二朗氏
株式会社グリーンスペースオオサカ
庭プロデューサー&庭師 / スペシャリストタイプ
憧れの存在として、兄・耕造氏は糸井重里、みうらじゅん、横山健を、弟・二朗氏は村上春樹と中崎タツヤを挙げる。

紙とフェルトで描き出す、ボーダーレスな生き方のカタチ
トヨクラタケル氏
Re:VERSE
イラストレーター・画家 / スペシャリストタイプ
憧れの存在はフランシス・ベーコン。

ものづくりから届け方まで、プロセスをデザインする野心
福嶋賢二氏
AZUCHI / KENJI FUKUSHIMA DESIGN
クリエイティブディレクター・デザイナー / プロデューサータイプ
提案時に意識するのは「余白を残すこと」。
司会

中川悠氏
株式会社きびもく / NPO法人チュラキューブ

森口耕次氏
AUN CREATIVE FIRM
仕事において守るべきこと、譲れないこと。
「自分たちの指標となる12ヶ条を明文化しています」(大垣氏)

森口氏
僕は、この「OSAKA UNDER40 CREATORS」の冊子企画にあたって、「これからのクリエイターは、スペシャリストタイプかプロデューサータイプの2つに分かれていくだろう」と考えました。僕自身どちらにもなれていない器用貧乏なタイプ(笑)だからこそ、みなさんの考えを聞いてみたかったというのが出発点です。

中川氏
今日のテーマは、ここにいらっしゃる5組の苦労や悩みや達成などのヒントを、彼らに続く未来のクリエイターに届けていくことだと思っています。まずひとつめの質問は「仕事をする上で大切にしていることは?」です。

池田氏
基本的に仕事でも展示でも「何をするか」以上に、「誰とするか」だと思っています。クライアントであれスタッフであれ、ものごとに取り組む温度感や人間性、見ている先など、フィーリングが通じ合う部分を大切にしていますね。

中川氏
大垣さんは仕事をする上での優先順位をあえて言語化していますね。

大垣氏
優先順位は一に「その思い」、二に「ブランドを作るという価値」、三に「利益」。これは、自分たちの指標となるものを明文化するために作った「アシタノヤクソク」っていう12ヶ条のうちの一文です。ある仕事をすべきか・すべきでないか判断を迫られるときのモノサシになるものですね。たとえばスタッフに「これはどうしてもやりたい、やるべき仕事だ」という思いがあるなら、それは一番に優先されるべきだと思っています。次に僕たちが息長く仕事をしていくためには「ブランド価値を作ること」や「利益」も必要です。3つの条件を満たすのが理想の仕事ですが、その都度ケースバイケースで、線引きはむずかしいですけどね。


辰己氏
僕らは「お客様にも自分にも正直に」ですね。というのは僕らの仕事は、自然を相手に作っていくわけで、その場しのぎのウソをついてごまかすことなんていくらでもできてしまうし、実際そういう業者も多いんです。適当に庭を作って「5年後によくなります」と言いながら、実際には5年間も付き合う気なんてないとか……。だから僕たちは、どのお客様の庭も自分たちの庭だという気持ちで作るし、植物が言うことを聞いてくれないときは自分たちの力が及ばなかったことを正直に話しますね。

トヨクラ氏
僕は「スピード感と丁寧さ」。基本的に商業イラストは、与えられたオーダーに、限られた納期でいかに的確に応えるかを意識しますね。そのためには、依頼が来たときにさっと対応できるよう、普段からいろんなアイデアをストックしています。
一方で美術作品制作は、スピード度外視で「掘っていく感覚」。あともうひとつの活動であるプロダクト制作に関しては、もう「ひとりメーカー」なので、こんな商品を作りたいと思いついたら、すぐ工場に発注かけてJANコード取って、お店に営業します。とにかく納品のスピードが速いのでお店にはびっくりされますね。


福嶋氏
僕は「先生と呼ばれる関係性を作らないこと」かな。クライアントさんとはフラットな関係で考えたほうが物事はスムーズに進むと思うんです。プロダクトデザインって、たとえばプラスチック製品なら成型の型から作らないといけなくて、ちょっとした修正が時間や予算に大きく響いてくるので、最初のコミュニケーションや立ち位置の決め方はすごく大事。いいものをより早くリリースできるようにするためには、本音を言いやすい関係を作る必要があると思います。
チームで強くなるか、個人として強くなるか。

中川氏
次にお聞きしたいのは組織についてで、仕事の規模が大きくなるにつれて「自分でやるかチームでやるか」という選択を迫られると思うんですが……。

池田氏
うちは今、僕を含めて5名で、今後は10名程度までのチームをイメージしています。今の社会や組織って、制作スキルもコミュニケーション能力もまんべんなく満たす人間が求められている気がするんですけど、僕はそこに疑問を感じて独立したという経緯もあって……。たとえどこかいびつでバランスが欠けてても、何か突出した能力を持つ人に魅力を感じるんですね。そういう人材を集めて「集合体として強いチーム」をめざしている感じです。

大垣氏
僕が独立したのも、そのあたりがカギになってる気がします。往々にして会社という組織では、個々のクリエイターが自分の理想を追求しようとしてもストッパーがかかってしまう面がある。でも僕はそれはむしろリスクかなと思うようになって。僕らのような広告制作の仕事は、やはりチームでないとやれないものが多い。だから「チームで強くなる」ことを目指すには、個々のスタッフにある「思い」や伸びたい方向性を邪魔しない方がいい、という仮説に立って会社を運営しています。僕もできれば経営をせずして、好きな仕事を自由にやり続けたいっていう思いがあるので、そういう意味では会社は一種の「実験」ですね。

トヨクラ氏
僕は個人で自宅を仕事場にしてやってるので、家から出ることもほぼなくて、今日は2ヶ月ぶりに電車に乗ったぐらい(笑)。できる限り自分でやってしまいたがる傾向があるので、スタッフ抱えてるってすごいなと。

森口氏
僕もまったく一緒で、自分で全部やってしまいがちです。作るのが楽しいから人任せにしたくないと思ってしまう。
ブレイクスルー前の、もがいていた時期にやったことは?
「先代の取引先を全部断りました」(辰己兄弟)


辰己氏
僕らが家業を継いだ頃は、造園の仕事だけで食べている人は関西ではごく少数で、ゼネコンの下請けをしたり、公共工事で街路樹を切ったり、同業者の手伝いをして日当稼いで食いつなぐのが常識みたいになってました。でも僕らは庭一本で食べていきたかったから、日当稼ぎの仕事はしないと兄弟で決めて、親の代からの付き合いも全部断ったんです。おかげで全く仕事のない時期が2~3年続きましたが、その期間はクリエイターの交流会とか、ふつうの庭師が行かない場に行って自分たちの活動を伝えるようにしていました。昔と違って、一般の方と庭師の間にほとんど接点がないのが現状ですし、同業者同士の横のつながりもなかったので、「ニワプラス」っていう関西の若手造園家の集まりを主宰して、いろんな発信をするようにしたり……。


大垣氏
今もそうですけど、「面白い仕事」が向こうから「お願いします」ってやってきたりはしないんですよね。だから常に、頼まれた仕事をそのまま打ち返すのではなく、ちょっとタガを外すというか、条件や現実性を度外視して、「こんなことになったら面白いですよね!」っていうアイデアを必ず添えて持っていくようにしています。そうすると、ひととおり仕事が終わったあとに、相手の記憶に「あの人なにか面白いこと提案してくれたな」ってのが残って、次のチャンスにつながっていくと思います。「超えろ。カンテレ」のハチエモン宇チュー企画なんてまさにそうです。

次なるクリエイティブの種をいかに見つけるか。
「作家がめざす未来を共有し、そこから逆算して考える」(池田氏)

中川氏
池田さんは、もがいている時期はできるだけ人に会ったり考える時間を作る、と答えていますね。

池田氏
うちはondoというギャラリーをやっていて、ひと月一組の作家さんと展示を作り上げていますが、テーマに合わせてプロダクトを作るなど、展示だけでない広げ方を心掛けています。といっても僕らがディレクションしているつもりはなくて、やっていることはヒアリング。作家さん自身が5年後10年後にどうなっていたいのかを、時には一緒に飲みながら時間をかけて聞いて、目的を共有した上で、そこから逆算してうちの展示で何をやるべきかを考えます。

中川氏
そういうインプットの時間って、みなさんはどんなふうに意識しているんでしょう?

トヨクラ氏
僕はいろんな展覧会にまめに足を運んだり、新聞をじっくり読み込んだりですね。時事問題に触発されることが多いので、制作しながら国会中継をずっと流してたりします(笑)。

福嶋氏
ふだんからいろんな売場を見て歩きますし、気になる企業があれば、ウェブサイトを隅々までチェックして情報収集します。もちろんお目当ての企業に一発で話が通ることなんてまずないので、どうすればこの企業にたどり着けるか、どういうふうに話を持ち掛けたらうまくコトが進むか、かなり考えますね。
たとえば今「5年以内にここの仕事に呼ばれるようになりたい」と思っているブランドがあるんですが、昨年は丸1年、そこのブランドプロデューサーの方が東京で主催されていた研究会に毎月通っていました。関西からの参加者は僕ひとりでしたけど、そうやって自分を知ってもらえたおかげで別のプロジェクトに声をかけてもらえましたし、そういうことにはエネルギーを惜しまないですね。

未知の領域に取り組む時こそチャンス。
「既存の手法を疑ってパラダイムシフトを生む」(福嶋氏)

中川氏
未知の領域の仕事に取り組む時の、自分なりの流儀って何かありますか?


辰己氏
僕らは自分たちでプランニングも施工もして、そこから長期間にわたってお手入れをさせてもらうっていうスタイルなので、どうすればそういう自分たちらしい関わり方ができるかを考えます。そのためには依頼主であるクライアントさんのこともけっこう調べますね。

福嶋氏
僕は「好奇心を持つ」ことに加えて、見せ方や販売拠点含めて、「既存の手法を疑う」ことが大事だと思っています。たとえば今ある和紙メーカーと進めているのは、和紙の履歴書を神社仏閣で売ろうというもの。ちゃんとご祈願もしてもらって…。履歴書ってコンビニで買えば100円200円ですが、それなら800円でも売れますよね。それも、どこででも手に入るんじゃなくて「そこに行かないと買えない」という拠点を国内3か所ぐらいにしてしまうと、逆に面白いと思うんです。
これまでにあった、人生最大の転機は?
「法律の道を捨てて絵の道に進むと決めたこと」(トヨクラ氏)

中川氏
ではみなさんにとっての「人生最大の転機」についてお聞きしたいんですが……。

トヨクラ氏
うちは祖母が日本画家、祖父が弁護士で、僕も弁護士めざして大学の法学部に通っていました。祖父母ふたりを見ながら育って、どっちの道に進むかについてはかなり揺れましたが、「絵では食っていけない」と言われて、一旦はあきらめたんです。でも大学4年の時、知り合いの建築家に「やってみたら」って背中を押されて、ずっとカギをしてた「絵を描きたい」って気持ちが一気に開かれて、「もうどうなってもいいから絵の道に進もう」と決めたんです。


辰己氏
僕らにとっては先ほども話したように、父の代からの付き合い仕事をすべて断った時ですね。周囲の先輩方も本心では庭だけで食べていきたいと思いながら、住宅が減ってる中でそんなのは無理だと言っていて。でも僕らは、どうせならみんなが無理だと言ってることに挑戦してみようと決めたんです。周囲にこそいなかったけど、全国的に見れば庭に特化して食べてる方々はいらっしゃるので、僕らにだってやれるはずだと。初めは「お前らアホちゃうか」って言われましたけどね。

中川氏
福嶋さんは「転機はこれから」だとおっしゃっています。

福嶋氏
僕にはまだ爆発的なヒットもないので、あの商品イコール私、と言えるようなものはまだできてないと思っています。

大垣氏
僕も同じで、仕事上で劇的な転機があったという実感はないですね。自分的にはコツコツ掘り続けていたら、入り口が開通してここに到達していた、みたいな感じです。ずっと言い続けてきたことが3年がかりで実現したとか……。
画廊でも、貸しギャラリーでもない、オリジナルな「発信の場」をデザイン会社が持つ意義とは?

中川氏
ondoやアシタルームといった「場」を持つ面白さやむずかしさについてはいかがですか?

池田氏
うちはあくまでデザイン会社として、社会にいかにアートやイラストレーションを広げていくのかを考えていますが、続けていくためには実際に販売面でも結果を出さなければという課題はあります。
とはいえ僕らのミッションは、同世代や下の世代の作品を発信して、彼らに活動の場を提供していくことなので、その辺はバランスをとりながらやっています。展示で生まれた関係性が仕事につながることもありますし、単体で採算を合わせようという意識だけではないですね。


大垣氏
アシタルームはギャラリーというより「作戦会議室」で、我々が今後やってみたいことをカタチにして発信するための部屋です。作家さんに展示してもらうだけでなく、必ずうちと何かしらのコラボレーションをするんですが、どっちかというとその実験が主な目的と言っていいぐらいで、クリエイティブの実験場・ラボと最近は言ったりしています。だから出発点はまさに「思い」で、時にはまったく作家活動をしていない人とコラボすることだってあります。
新しい価値軸で未来を創っていく、それぞれの意志。

中川氏
では最後に、これからの展開についてそれぞれお聞かせいただけますか?

福嶋氏
今後は、屋外のベンチや街灯などといった、公共的なものも手掛けていきたいですね。まだデザインが入り込めていない分野において、これからの若い方たちのデザインの土壌を開拓する、「作る機会のデザイン」とでもいうんでしょうか。


辰己氏
僕らは日々目の前にあることを丁寧に、ということに尽きるかな。あとは僕らもどっちかというと受注側の仕事なので、何か自分たちから発信したり、既存の形を変えるようなことができればいいなと思います。

トヨクラ氏
5年先の未来なんてまったく見えてないですが、とりあえず面白いと思ったことはどんどんやっていくつもりです。商業イラストと美術作品制作とプロダクト制作という3本柱が、うまく絡み合ってくれればいいなと思います。

池田氏
僕らは今ちょうど台湾でondoとして2か月間限定展示をやらせてもらっているんですが、LCCを使うと台北との往復が1万8000円、東京往復するより安いし近い、っていうのが意外な発見で……。台湾のマーケットにも注目しているので、現地でいろいろ見て回っていますし、国内ではondoとG_GRAPHICSの東京展開も考えていて、自分たちの手の届く範囲で丁寧に発信できる拠点を作りたいと考えています。

大垣氏
僕も福嶋さんと同じく、デザインがまだ弱い公共・福祉分野の仕事をやってみたいですね。最近では仕事の範囲が、広告制作だけでなくブランディングや商品開発、プロダクト制作にも広がってきています。商品開発してパッケージ作ってプロモーションして……とすべてをうまくブリッジさせながら、総合的にクリエイティブを作れる会社になっていきたいです。

森口氏
こうして話を伺ってみて、改めていろんな発見や学びがあって楽しかったですし、すでに冊子に描かれてる内容よりも、さらに皆さんが進化していることを実感しました。

中川氏
ここにいるみなさんのように、新しい価値軸で未来を作っていく意志を持った方々が、5年後10年後の社会でどんなふうに進化を続けているのか、僕は非常に興味があります。大阪にはまだまだ面白い方がいっぱいいらっしゃいます。どうかみなさんもいろんな生き方に触れて、新しいクリエイティブを作っていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。

イベント概要
OSAKA UNDER 40 CREATORS ふたつのタイプから考えるこれからのクリエイターのあり方 Vol.2
クリエイティブクラスターフォーラム
メビック扇町では今年2月、大阪で活躍する40歳以下のクリエイターを紹介する冊子「OSAKA UNDER 40 CREATORS INTERVIEW」を発行しました。冊子では、これからのクリエイティブシーンをリードしていくクリエイターを、全体を見通す力で仕事をつくる「プロデューサータイプ」と、唯一無二のスキルで仕事をつくる「スペシャリストタイプ」という、ふたつのタイプに分けてご紹介しました。
本フォーラムでは、冊子でご紹介したクリエイターをゲストに招き、それぞれの働き方、仕事に対する考え方をより掘り下げるとともに、今後のクリエイティブシーンを活性化していくために必要なことなどについて、同世代のクリエイター同士で意見を交換し、議論を深めます。
開催日:2016年8月8日(月)
池田敦氏(いけだ あつし)
G_GRAPHICS.INC
企業のプロモーションやブランディングを手がける一方で、「社会に開かれたデザイン事務所」をめざし、2013年からはギャラリー&プロダクトレーベル「ondo」も運営。若手作家とともに作品発信やプロダクト制作に取り組み、東京・台湾でも展示を行うほか、商業施設の催事プロデュースなど活動の幅を広げている。

大垣ガク氏(おおがき がく)
アシタノシカク株式会社
視覚クリエイティブを基点に、一貫した世界観のもと、さまざまな施策をつないでコミュニケーション効果を最大化する「ブランディングブリッジ」を提唱し、国内外の広告賞受賞歴多数。2015年からは「自分たちの興味関心を追求するリアルオウンドメディア」と位置づけるスペース「アシタルーム」も運営している。

辰己耕造氏・二朗氏(たつみ こうぞう・じろう)
株式会社グリーンスペースオオサカ
八尾市で祖父が始めた造園業を受け継ぐ3代目兄弟。設計から施工、メンテナンスまで一貫して行うスタイルで、個人住宅や病院・施設などの作庭を手がけるほか、関西若手造園家の集まり「ニワプラス」立ち上げ(※2016年春卒業)や、講演・ワークショップなど多彩な活躍が評価され、2014年八尾市文化新人賞受賞。

トヨクラタケル氏
Re:VERSE
紙とフェルトを用いた、ユーモラスでシュールな作風が持ち味。書籍や広告などの商業イラストのみならず、現代美術作家として作品を発表したり、オリジナル雑貨ブランド「Re:VERSE PRODUCT」を展開するなど、3つの異なる領域を自在に行き来しながら、イラストレーターとしての生き方の可能性を広げている。

福嶋賢二氏(ふくしま けんじ)
AZUCHI / KENJI FUKUSHIMA DESIGN
2011年独立。文具、家具、家電などのプロダクトデザインから、パッケージデザイン、空間デザインまで総合的にアプローチ。2014年に設立したクリエイティブスタジオAZUCHIは、デザイナーに加えて、販路開拓を行うバイヤー、翻訳・海外展開に関するアドバイザーを擁し、ブランド価値創出をトータルに担う。

中川悠氏(なかがわ はるか)
株式会社きびもく / NPO法人チュラキューブ
タウン誌編集やアートギャラリー運営などの経験をもとに、2007年に起業。障がい者の就労・生活支援や地域のコミュニティ再生、地域産業の活性化といったさまざまな社会的課題に、編集の思考で寄り添い解決しようとする「イシューキュレーター」。

森口耕次氏(もりぐち こうじ)
AUN CREATIVE FIRM
2010年の独立以来、デザインのみならず撮影、取材、執筆までこなす独自のスタイルで、企業や商店などの商業デザインはもとより、情報発信のメディアづくりにも力を注ぐ。「OSAKA UNDER40 CREATORS」冊子では、編集・取材・アートディレクションを担当。2016年大阪より徳島県神山町に移住。
2018年にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

公開:
取材・文:松本幸氏(クイール)
*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。