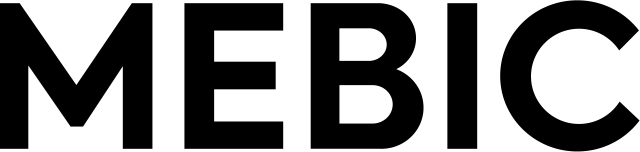らしさ、結果、世界観からみる私のクリエイティブ現在地
三団体 三世代 トーク三昧 第六弾
いつもはチームとして、ひとつの広告と向き合うカメラマン、デザイナー、コピーライターがそれぞれの立場から語り合う。6回目の開催となる「三団体 三世代 トーク三昧」は、関西クリエイティブ業界の三団体、「日本広告写真家協会(APA)」「日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)大阪」「大阪コピーライターズ・クラブ(OCC)」によるコラボイベント。今回は「じぶんらしさ」「結果の出し方」「世界観」を各世代のテーマにして展開された。世代ごとに、業種ごとに悩みや大切にしていることは変わっていく。3時間にわたるトークから見えてきた、それぞれの本音とは。
第1部:各団体の若手同士が語る「じぶんらしさの出し方」

スピーカー

[APA]原田雄介氏
Photo Studio OLIVE

[JAGDA]南部真有香氏
有限会社テイスト

[OCC]宮坂和里氏
株式会社博報堂
ファシリテーター

[JAGDA]細川誠明氏
A.D.GRAPHICA Co.,Ltd.

細川氏
第一部の司会を務めますグラフィックデザイナーの細川です。まずはみなさんの自己紹介からお願いします。

原田氏
カメラマンの原田です。企業のウェブサイトの撮影がメインで、スタジオに自分でセットを組んでのイメージ撮影をおこなったりもしています。

南部氏
ふだんはブランディングを中心に、グラフィックデザイン全般の仕事をしている南部です。ときどきタイポグラフィーの個展も開催しています。

宮坂氏
博報堂でコピーライターをやっている宮坂です。とはいえ時代的に新聞広告やラジオCMが減っているので、今は動画の企画や、CMプランナーのようにコピーを中心としながら頑張っているところです。

細川氏
今回は「じぶんらしさの出し方」というテーマですが、そもそも「じぶんらしさ」を仕事で出していますか?

宮坂氏
コピーライターはポエマーじゃないので、自分らしさを出さないイメージがあります。個人的には「出そうと思ってはいけない」くらいの気持ち。クライアントのやりたいことに対して、正解を探すことが仕事だと思っているので。ただ、ここまで頑なに抑えているということは、逆に「じぶんらしさ」を欲してるのかも。

細川氏
本当は「じぶんらしさ」が欲しいと。

宮坂氏
誰しも不安だから欲しくなっちゃうけど、職業的に「らしさ」が先行するのは絶対にいけないから、「作風」とか言い出す同期を睨んじゃうみたいな(笑)。デザイナーやカメラマンとは全然違う気がします。

南部氏
私は意識しなくとも勝手に滲み出ている気がします。ブランディングであれば、タイポグラフィーを基本に考えますし、グラフィック的なものでいえば有機的で曲線的なデザインになるところとか。


細川氏
絵づくりのスイッチポイントが、写真やイラストといったビジュアルよりも文字の表現なんですね。「じぶんらしさ」の出しどころも難しいですよね。コピーライターやデザイナーの仕事は、プロジェクトの初期段階からクライアントに近いところからスタートするのに対して、カメラマンはいろいろ決まってから依頼されることが多いでしょ。

原田氏
だからこそ商品の歴史や制作意図、こだわりはしっかり聞き、意識して表現するようにしています。結果、それを気に入ってもらえたら、ある意味「じぶんらしさ」は出せたのかなと思います。

細川氏
そもそもクライアントは「らしさ」を欲しがっているんですかね。指名で「この人にお願いしたい」というときは、ほかとは違う何かを求められていると思うんですが。

宮坂氏
クライアントやCDからの指名は以前の仕事を見て、そこから「らしさ」を拾っていただくのかもしれない。自分が意図的にやったブランディングで選ばれたというより、過去作から判断してもらっているのが実情だし、それは正しいのかなと思います。


南部氏
デザイナーも同じですね。今まで制作したものを見て、クライアントは「この人なら、こういうものが出てくるだろう」と予想して依頼されると思うので。

原田氏
僕はどちらかというと、人柄で仕事をもらうことも多いんです。学校案内の撮影が多いんですけど、生徒とのコミュニケーションに力を入れてて。トーク8 : 撮影2くらい(笑)。そうやって被写体との距離感をぐっと近くして緊張をほぐし、その人らしい表情を引き出してます。

細川氏
原田さんの話で興味深いのは作品だけではなく、制作過程でも「じぶんらしさ」もあるという点。それも確かに仕事を生み出す、ひとつのきっかけかなと思います。仕事への取り組み方で「これは自分ぽいな」と感じることはありますか?

南部氏
わりと几帳面に仕事を進める方なので、そこは自分らしいかな。少しでも疑問が湧いたら、すぐにクライアントに質問しますし。そういう密なコミュニケーションをとることによって、成果物と求められるものとのズレを無くしていけると考えていますね。

宮坂氏
逆に私は抜け漏れが多くて、提出物もちゃんと出せなかったり。そこは馬力で挽回してます(笑)。めっちゃ頑張って案も出すし、熱意も凄くあるからたまにスポーンって抜けても許されたいというか、バランスとろうと思っています。それとリールを選ぶときは好きな作品を優先するので、それが意図的に「らしさ」を出している瞬間なのかな。

細川氏
そのコントロールは大切ですよね。ちなみに新人の頃はどういう風にアピールしていましたか。

宮坂氏
私の新入社員時代は、博報堂の社内にまだ師弟制度があって、師匠のような人について学ぶという形でした。好きなことはプロフィールに書かせてもらったりするんですけど、好きなことと好きな表現はまた違ったりするじゃないですか。

南部氏
若い頃はコンペに積極的に参加したり、架空のロゴやオリジナルのタイポグラフィーをつくってSNSで発信したり、やりたいことをアピールしていました。

原田氏
カメラマンは作品づくりを積み重ねていくしかないですね。自分が好きな風景も撮りますが、まずはどういう作品が撮れて、どういうライティングができるかをアピールする。僕はあまりやらなかったけど、今ならSNSにどんどん上げればいい。自分の広告になるし。

宮坂氏
そういうときって、「こういう仕事が来るかな」とか念頭に置いて撮るのか、それとも「好き」を優先して撮るのか、どっちなんですか?

原田氏
僕は結構計算してます。営業でも「この作品はこういうことを表現したかったんで、ライティングはこうして」と説明しやすいので。

宮坂氏
それで成功した経験ってありますか?

原田氏
「料理をつくったり撮影するのが好き」と料理の画像をサイトに上げてたら、ふるさと納税の料理の仕事が入りました。結局「こんな仕事やりたい、こんなの撮りたい」と言い続けるのも、自分らしさを出す方法なのかなと。


細川氏
原田さんは独立されているから、営業的な意識も高いんですね。ところでこの業界には個性豊かな先輩って大勢いるじゃないですか。ある意味、個性=らしさだと思うんですけど。憧れる先輩とかっていますか?

宮坂氏
面白くてチャレンジングな動画をつくる先輩がいて。それがあるとき、真面目に人に寄り添う企画で賞を取ったんです。らしさって仕事を依頼されやすいという点ではメリットかもしれませんが、「こっちもできるんだ!」という万能感がカッコいいなと。

南部氏
知り合いのデザイナーは、どんなものでも一目でその人の作品だと分かるんです。どの仕事でも個性がはっきり表れていて。ほんと凄いなと思います。

原田氏
同じように、「一目で誰の作品か分かる」カメラマンは憧れですよね。僕もいつかは「これ撮ったのは原田くんかな?」と思ってもらえたら。

細川氏
それは僕も憧れます(笑)。先ほど先輩のお話を聞きましたが、逆に後輩へ「じぶんらしさ」についてアドバイスするとしたら、どんな話をしますか。

宮坂氏
コピーライターなら、絶対「らしさなんか考えないで」。特に若手のうちは妨げにしかならない。いかに面白い、いいものをつくれるかだけに集中して、その結果、成功が重なって「らしさ」が形づくられていくのが理想です。

南部氏
学生のうちは授業でいろんな表現を体験するので、自分の専門分野以外にも触れてみるとか。そして卒業制作で自分の好きなこと、やりたいことを出していけばいいのかな。すでに好きなものがあるのなら、それを突き詰めるのもありですね。

原田氏
「好きなものをどんどん出していけ」ですね。カメラの性能が非常に上がり、知識があれば誰でもそれなりの写真は撮れる。そこから突出するため必要なのが個性や自分らしさの表現だと思うので。

細川氏
まさしく三者三様。それと仕事を取りに行くときと着手するときとでは、「らしさ」の活用方法が違うのも興味深かったです。
第2部:各団体の中堅同士が語る「結果の出し方」

スピーカー

[APA]望月研氏
cool beans

[JAGDA]峠田充謙氏
デザイン峠

[OCC]細田佳宏氏
タイガータイガークリエイティブ
ファシリテーター

[APA]石田ひろあき氏
株式会社POP GRAPHY

石田氏
フレッシュな若手から一転しまして(笑)、ここからはぐっと渋め中堅の部となります。進行を務めます、カメラマンの石田です。

望月氏
カメラマンの望月です。山梨で生まれ、大学で東京に出てNHKに番組ディレクターとして就職しました。退社後、ファッション・グラビアや建築系のカメラマンのアシスタントを経て2004年よりフリーになり、2012年に仙台へ、2022年からは京都へ移住して活動を続けています。

峠田氏
イチから考えることが好きな、グラフィックデザイナーの峠田です。今年51歳になります。大学卒業後、頭髪化粧品会社で17年ほどインハウスデザイナーをしていました。

石田氏
独立されたのは何歳のときですか?

峠田氏
40歳の誕生日に辞表を出しました。30歳くらいから「辞めよう」と思いつつ、メーカーってひとつのプロジェクトが終わったら、もう次のプロジェクトが始動するので、辞め時を見つけられず。ちょうどスコンと空いたのが、このタイミングだったんです。

細田氏
「タイガータイガークリエイティブ」というクリエイティブエージェンシーで、CMプランナーをやっている細田です。今52歳なんですが、広告制作の世界に入ったのは35歳で、まったく畑違いからの転職。それまでIT企業のプログラマーとかエンジニアをやっており、コピー機のプログラムを書いてました。ある意味、コピー三昧(笑)。

石田氏
CMプランナーというのは、どういったお仕事をされるのですか?

細田氏
ストーリーをつくり、シナリオを書く仕事ですね。みんな大好き関西電気保安協会の仕事では、昔のCMのノリも大好きなんですけど、「カッコいいイメージで」という要望に応えるものにしました。カッコイイものやエモいCMもつくりますが、個人的に基本はみなさんに笑ってもらえる作品をつくりたいと考えています。それが「じぶんらしさ」かなと思っています(笑)。
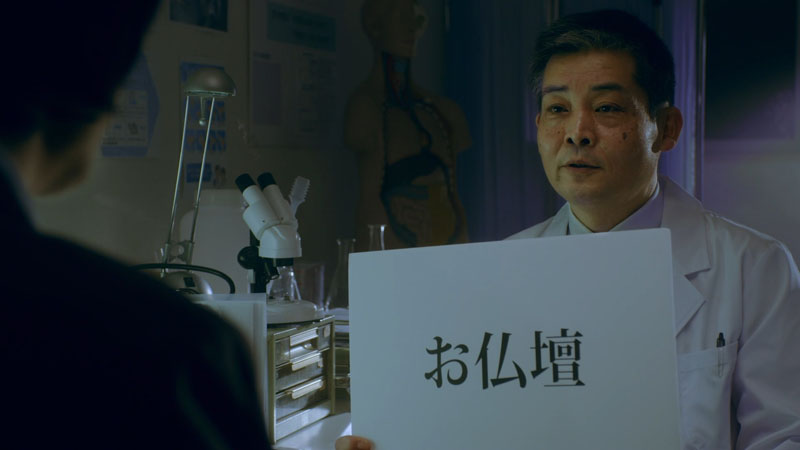

石田氏
(笑)なぜここで、若手チームのテーマを?

細田氏
中堅の部で呼んでいただきましたが、まだ新人気分が抜け切れないもので。

石田氏
今回のテーマは「結果の出し方」ですが、そもそも「結果」って何なんでしょうね。まずはそこから定義しましょうか。

峠田氏
いわゆる仕事の結果だけでなく、「今までやってこれたこと」もひとつの結果といえるのかなと感じました。

望月氏
人生はまだ途中だけど、失敗しながらもそれなりの結果を残してこれたから未だにカメラマンをやっていられる。そういう意味では結果は出てるのかなと。

細田氏
まだ話せるところまでたどりつけてないですね、人生については。

石田氏
さっきの自己紹介で面白いなと思ったのが、望月さんも細田さんも最初からこの職業をめざしていなかった点。どのタイミングで転機が訪れたのですか。

望月氏
大学時代に言語を学んでいた東南アジア方面に、よく旅して撮影もしていたんです。20数年前の東南アジアなので、それなりの写真が撮れてしまうんですね。「これで食えるんじゃないか?」と勘違いしたのがはじまり。就職してからも心の片隅にその思いがあって。いずれファッション系のカメラマンになりたかったのですが、当時はアシスタントになれるのが25、26歳までという年齢制限があったので、退職してこの世界に飛び込みました。


細田氏
僕はインターネットの黎明期に大学を卒業して、「ネットとかIT系って面白そう」と就職したんだけど、10年くらいして壁にぶち当たりまして。ちょうどその頃、隣の席の人が「宣伝会議賞」の募集が載っている雑誌を見せてくれた。興味が湧いたのでお遊びで何本か投稿したら、2次審査まで通り、広告を意識しだしたのが31、32歳。それまで広告って、その会社の人がつくってると思ってたくらいで、電通も博報堂もよくわかってなかったんです。

石田氏
広告にまつわる仕事のなかで、CMプランナーを選んだのはどうしてですか?

細田氏
大学生の頃から、映画やお芝居、小説などの創作が好きで、自主製作映画や演劇を趣味でつくり続けてて、それこそNHK受けて落ちたんですけど(笑)。広告に興味持って調べていくうちに、これは自分に合ってると。劇団でもアイデアはあるけど長い話がつくれない自分にとって、短いCMはぴったりな気がしたんです。

石田氏
峠田さんはいつ頃からデザイナーをめざしていたんですか?

峠田氏
中学生ですね。美術の教科書に載っていたカッサンドルというデザイナーの作品を見てカッコいいなと思って、その頃からレタリングやったり。メーカー在籍時はパソコンの知識もないまま、いきなりMacを与えられて何かつくれという状況で。それでグリコのロゴや牛乳石鹸の赤箱のデザインをされた奥村昭夫さんがいた大阪の「IMI / インターメディウム研究所」の門を叩き、会社員として働きながらグラフィックデザインやアートの勉強をスタートさせました。そこからデザインがどんどん楽しくなってきて、公募に出品してみようとか意欲が湧いてきたんです。


石田氏
話を戻すと「広告の結果」ってどういうものだと思いますか?

望月氏
世間で話題になっても、それが「お客さんのためになったか」どうかは分からないという意味では、「広告の結果」って、よく分からない。とはいえ「お客さんのため」を第一に考えてやっています。

石田氏
具体的には?

望月氏
撮影でいうと、事前の準備は極力つめて、スタート1本目のテストカットはカンプにほぼ近いものが出せるようにする。要するにカンプに近づけることを目標としない。カンプをスタートにすることで、そこから自由度が出ますし。ですから準備が8~9割、現場では頭にあるものを再現していくだけで、その場での出会いや面白いハプニングがあれば取り入れる、という風に余裕を持てるようにしていますね。

峠田氏
僕は「本質」という言葉が大好きで、それをどう見極めるかがポイントだと思って仕事をしています。「人はみな、口下手」だと思っていて、たとえ話が上手いか下手かだけで、「本質」を突くことが出ればそんなものは不要で。「たとえ話の向こうにあるもの」をつかみたい。そのアイデアが出た時点で、どうしてもビジュアルの表現はシンプルになりますね。

細田氏
CMはみんなが楽しんだり、覚えてくれたり、浸透したり、それが結果だと思っている。ですから「世の中の興味」「自分のやりたいこと」「クライアントのやりたいこと」、この3つの円が重なる場所を必死で探し続けています。日々、探し続けることが、結果の出し方。そこで導かれた結果に対して、「思ったほど反響がなかった」とか「意外なほど売れた」などを見極めながら修正しつつという感じです。

石田氏
最後に、今後のビジョンについて教えて下さい。

峠田氏
明確なビジョンはないですね。僕は会社を退職した時点で「先のことはどうなるかわからない」と悟っているので(笑)。このときから、将来について考えるのはやめました。「向こう3ヶ月ずつ更新する」、そんな生き方のほうが人生を楽しめますから。

望月氏
僕も同じですね。若い頃は「このファッション誌で撮りたい」とかあったんですが、だんだんそういうのもなくなっていって。気持ちよく仕事は続けたいので、一緒に仕事する相手は選んで。最終的には、地域の人といい関係を持てる「写真館のおやじ」になりたいと思っているんですよね。

細田氏
目標を立ててもそこに行かないのはわかっているので、先のビジョンはないですね。現場ごとの仕事のクオリティを上げていくのが最前提なので。その先に、自分の知らないもの、今まったく予想してないものができればいいかなと思っています。30歳で人生の目標変えたように、10年経ったら変わってくるかもしれない。飽きてしまうかもしれない。自分の好奇心のおもむくままに生きていきたいと思います。
第3部:各団体のベテラン同士が語る「世界観の見つけ方」

スピーカー

[APA]奥脇孝一氏
オクワキスタジオ

[JAGDA]清水柾行氏
青空株式会社

[OCC]田中有史氏
旅する田中有史オフィス
ファシリテーター

[OCC]鈴⽊契氏
株式会社電通

鈴⽊氏
電通でコピーライター、CMプランナーをやっている鈴木です。今回ベテランのみなさんのファシリテーターということで、頑張らせていただきます。

奥脇氏
カメラマンの奥脇です。山梨の出身で東京時代は松井希通氏に師事し、大阪に来たのは1972年になります。ここでは福田匡伸さんにお世話になり、1980年に独立して今に至っています。

清水氏
「すべてはデザイン」という考え方のもと、さまざまなプロジェクトをやっているデザイナーの清水です。ジャンル関係なく、いろんなことに挑戦することをモチベーションに、幅広く活動をしています。

田中氏
コピーライターの田中です。地味に40年ほどやってます。僕はネーミングの仕事が好きで、今も残っているものとして「NU茶屋町」など、一度はみなさんの目に触れたものもあるかと思います。

鈴⽊氏
今回のテーマは「世界観のつくりかた」。これって第一部で語られた「じぶんらしさ」に近いかなと。作品そのものの世界観やセルフブランディング的な意味もありますよね。たとえば奥脇さんの作品を見ると「硬質な世界観」を感じますが、いかがでしょうか?

奥脇氏
「硬質な世界観」という言葉はとても嬉しいですね。でも世界観って自分だけでつくれるものじゃない。人に見つけてもらって引っ張り上げてもらって、一緒に仕事をするなかで生まれるものと思っていて。実は昨日、新しい仕事が入ってね。不安もありつつ、少しでも自分なりの匂いが残せたらと考えています。

鈴⽊氏
なるほど、世界観は自分で決めるべきではないのかもしれないと。清水さんのお仕事からは、「デザインという言葉の捉え方=世界観」かと思ったのですが。

清水氏
自分自身では「結果としてそうなった」としか認識できなくて。かつては奥脇さんのような硬質でビシッとした世界をつくりたい時代もあったんですよ。でも気がつくと、柔らかく、優しいものになってしまう。自分のなかのそういう要素が自然と表出してしまうジレンマもありました。

鈴⽊氏
そういうジレンマって、未だにありますか?

清水氏
今は「どうやってもそのままでしかないよね。これが僕だし」みたいな感じ。

鈴⽊氏
いつそういう心境になられたんですか?

清水氏
JAGDAに加入して変わったんですよ。20代の時はピッキピキのデザイナーで、「僕のこと見るな、触るな、話しかけるな」くらい、エッジが立ってた。それが30代でJAGDAの活動に巻き込まれて、「これはいろんな人の知恵や力を借りないとできない」という現場に入ったとき、性格や考え方が180度変わった。今まで閉じられるだけ閉じていたのが、いろんな正解があるんだと気がついてから、活動ベースとなり人の力を使わせてもらったデザインもするようになりました。


鈴⽊氏
田中さんのコピーは毎回あの手この手というか、こだわられていない感じがします。

田中氏
僕も「コピーライターは作風を持たないほうがいい」という主義で。もちろん作風が確立している方もいますが、僕には向かない。どちらかというと仕事仕事で「気持よく裏切ろう」と考えています。正直、コピーライターって世界観を持ってないと思うんです。ADとかカメラマンの作品に相乗りして世界観を借りてるぐらいの感覚じゃないですか。

鈴⽊氏
最初から、このスタンスだったのですか?

田中氏
僕は一生フリーランスなんかなりたくなかった。楽しくコピーを書いて給料を貰えればいいと考えていたのが、制作会社を突然クビになりまして。事務所を構えるにあたって、名前を考えないといけない。田中有史オフィスはいやだし、カッコいい横文字もなんかなあと(笑)。

鈴⽊氏
いやいや、そういうのが好き方もいらっしゃるので。

田中氏
とにかく自分を賢そうに見せるのが苦手で。その頃、ハワイアンシャツ好きが高じて、雑誌に取材されたんです。それで夏はほぼ毎日ハワイアンシャツで仕事してましたから、これをアイコンにすればいいとロゴをつくってもらって名刺にも載せて。とにかく「カッコよくならんとこ」というのが、僕の世界観です。

鈴木氏
みなさん、古いお知り合いだと思いますが、今までのお話を聞いて、自分が持っていたイメージに対する違和感とかありますか?

奥脇氏
実は仕事をご一緒したことはないんです。でもおふたりの仕事はよく見ています。僕がイメージする清水さんの世界観は、『わたしのマチオモイ帖』がとても強くて。小さな物語を広く展開される感じ。田中さんのは新幹線乗るときに、新大阪駅でおにぎり買うんですけど、いつもすごい行列でね……

田中氏
補足すると、このおにぎりは僕がブランディングした菊太屋米穀店のおにぎりのことです(笑)。

奥脇氏
そうそう(笑)。それと須磨海浜水族園の広告の印象が強い。小さいことの積み重ねというか。それとカウンターパンチ。一発食らわすイメージがあって、いつも面白く見ています。


清水氏
同じベテラン枠ですけれど、奥脇さんは少し世代が上で。この世代は、本気でクリエイティブをつきつめてきた気がするんですよ。僕たちやさらに世代が下がるほど、それを人がどう思うとか、どういうコミュニケーションツールとなり得るかといった「次の段階の活用術」に広がっている。それゆえに奥脇さんの「決定的なビジュアルや世界観」による、一点突破の手法は凄いと思う。

鈴⽊氏
なるほど。ベテランでも世代によって違いがあると。

清水氏
田中さんのお仕事は、さっき奥脇さんが言われたように、日常からいろんなものを見て、すくい上げて、共感をつくり続けている。正直、驚かされました。あれだけの数をつくろうと思うと、日常のシーンで何をどれだけ見ているのか。物の見方も違うし、見過ごしているものも見えているだろうなって。

田中氏
奥脇さんは僕が仕事を始めた時からスーパースターだったから、雲の上の人というか。本人は覚えてないですが、一緒に仕事したことはあるんですよ(笑)。清水さんの印象は、さっき昔はキャピキャピだったと……

清水氏
キャピキャピちゃいますよ(笑)。ピッキピキ!

田中氏
その時代は知らないので、プロデューサー思考の方という印象で。まわりを巻き込んだり、世の中にムーブメントをつくるのが上手な方だなと見てました。

鈴⽊氏
先ほど清水さんがターニングポイントを振り返られていましたが、みなさんもそういう転換期はありましたか?

奥脇氏
1980年に独立しましたから、フリーになってしばらくはバブル前夜で景気もよく、人生を甘く見ていました(笑)。仕事は順調でしたが、空いた日には作品づくりをして、おかげで四半世紀をかけてモノクロームの花の作品を撮り続け、NYで個展も開催できた。自分が変わった時期かもしれません。それとBRAUNのディレクターであるディーター・ラムスの回顧展では、800ページもの図録を手がけてNYのADCで金賞を受賞しました。私は「運鈍根」という言葉が好きで、コツコツやっているとこういうこともあるのかなと実感しました。


清水氏
23歳で何も知らずにこの仕事をはじめて、今に至っています。そこに関してはあるがままというか。さっき話したように自分の立ち位置が変わったから違う世界が見えて、気がつくと中身も変わっちゃったという感じですね。

田中氏
ひとつめは制作会社時代、大手家電メーカーの仕事をしたとき。「本物の広告の仕事ってこういうものか!」という緊張感を味わいました。これは自分の財産で、もう何があっても怖くない。2つめは「代理店の仕事はしない」と宣言したこと。となると自分で小さな仕事を取らなきゃならない。その積み重ねで今がある。それから神戸市がやっているセミナーに呼んでもらったときに、大学の先生と多く知り合えて、自分のやり方がまた変わった気がします。3つめは、神戸親和女子大学(現・神戸親和大学)の通信教育部の新聞広告や、話に出た菊太屋米穀店の仕事。「世界観ってこうやってつくればいんだ」と分かった。そのノウハウで今も食べている気がします。

鈴⽊氏
最後に「この界隈が失ってはいけないこと」について、ひとことずつお願いします。

奥脇氏
やっぱり対面、人と会うということじゃないですか。僕も若い頃は、そういうことを大事にしていなかった。最近はいらっしゃったお客さんと一緒にエレベーターに乗って下までお送りして(笑)。ここで意外と本音が聞けたりする。それがきっかけで親しくなったり、理解度が増すこともあると思うんです。

清水氏
結局のところ、「自分が本当に思っている心の声を聞くこと」かなと思いました。頭ではいろんなアイデアが浮かんでも、「それって自分が本心から望んでいること?」と問いかけ、そこにどれだけ忠実に答えたことが結果につながってきた。それが生き延びるための大切なポイントかな。

田中氏
失くしてしてはならない、いちばん大切にすべきなのは「達成感」。それと「セルフ・ジャッジメント」。最近、エビデンスとかマーケティングとか言いすぎなんじゃないか。消費者はセルフ・ジャッジメントしてものを買っているのだから、それに対して売る側のセルフ・ジャッジメントが錆びたらダメだと考えています。

イベント概要
写真のプロとデザインのプロとコピーのプロの、世代ごとのトークショー。
三団体 三世代 トーク三昧 第六弾
今回で6回目の開催となる「三団体 三世代 トーク三昧」は、関西クリエイティブ業界の三団体、「日本広告写真家協会(APA)」「日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)大阪」「大阪コピーライターズ・クラブ(OCC)」によるコラボイベントです。若手からベテランまで、写真・デザイン・コピーのプロたちが本音で語り合う「自分流仕事術」にご期待ください。
開催日:
公開:
取材・文:町田佳子氏
撮影:平野和司氏(APA)
*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。