メビック発のコラボレーション事例の紹介
IT企業、過疎の町へ。地域と会社、人と人をつないだオフィスデザイン。
バルトソフトウェア 津和野開発室

自然の中でのんびり働くプログラマ。業界の常識を変えるプロジェクトのはじまり。
人口約8000人、のどかな田園風景と歴史を感じる古い民家が建ち並ぶ島根県、津和野町。日が落ちて辺りが暗くなるころ、ぼんやりと温かな明かりが浮かぶ場所がある。バルトソフトウェア株式会社 津和野開発室だ。大阪に本社を構える同社が津和野に拠点を立ち上げたのは2015年1月。代表の山越正俊氏が、町長から津和野の過疎化について話を聞いたことが始まりだった。
15歳〜18歳という思春期まっただ中の頃の想い出は誰にとっても特別なものだろう。1年前の記憶は曖昧でも、当時のことは色鮮やかに思い出せるはずだ。山越氏がそんな多感な時期を過ごした場所が島根県津和野町だった。両親の仕事の都合で全国を点々としていた氏は中学3年生のとき、京都から津和野に転校。田舎特有の保守的な文化や親密な人間関係に戸惑い、「当時はイヤでイヤで仕方がなかった」と話す。数十年の時間を経て、再び津和野と繋がったのは、津和野出身者が集まる関西つわの会でのこと。町長から町の過疎化の話を聞き、軽い気持ちでIT企業の誘致を勧めたことがきっかけだった。ネット環境さえ整えばソフトウェアの開発は場所を問わない。それに自然の中で朝から日が暮れるまでのんびり働くプログラマというのも面白いかもしれない、そして津和野は地震が少なくBCM/BCP(事業継続)でのソフトウェア分散開発が実現できる、そんな想いから自社の開発室の立ち上げを決意した。しかしそこには、大きな問題があった。物件である。都心とは違い津和野には賃貸オフィスがない。町の人に相談すると空き家や廃業したスーパーを使ってはどうかと提案され、見つけたのが古民家を改造した元電気店だった。「これはどう見てもちょっとやそっとの改装では厳しい」プロの設計士に頼む必要があると判断した山越氏はメビック扇町に相談を持ちかける。選定にあたって出した条件はただひとつ、「津和野まで来てくれる人」だった。

新しいものとそこにあるものを共感しやすくする。それは、奇抜なものではなく、町に馴染む建物をつくること。
そこで白羽の矢が立ったのが、アンアーキテクツ一級建築士事務所の長澤浩二氏と荒木洋氏。「遠い所が好きなんですよ」と、二人が話すとおり、アンアーキテクツでは愛媛県のプライベートホテル「ヴィラ風の音」やイラクの母子病院「Maternity & Children’s Hospitalなど場所を問わず、さまざまなプロジェクトを手がけていた。二人は依頼を受けた後、レンタカーで津和野へ。「津和野は緑豊かで風情のある街でとても好感が持てたのですが、建物を見たときに予定していたコスト面で少し難しいかなと思ったことを覚えています」元々、普通の民家だったものを改修に改修を重ね住居付きの家電小売店に至ったその建物はかなり老朽化していました。断熱もなく、すきま風や光が入ってくる倉庫のような建物は、改修すれば一からつくるよりもかえって手間とコストがかかる。山越氏にとって初めての試みだけに「コストをなるべく抑えてほしい」という要望もあり、二人が提案したのは、外装は一切さわらず、間仕切りを取り払ってスケルトンにした内部に、すっぽりはいる箱のような空間を入れ込むということ。外装をいじらないのでコストが抑えられるだけではなく、町に建物がなじんで見えることを重視してのアイデアだった。さらに、ワークスペースは多角形の壁で囲み、通りから見える方の壁はステンレスの鏡面加工をしたものを採用した。観光客も地元の住民も通りを歩く人はみんな“なんだろう?”と窓を覗く。すると見慣れた自分の顔と町の風景が映る。「建物っていかに町になじむかが大切で、奇抜なものはつくらないほうがいいと思うんです。“町のランドマークになるように”という考え方もありますが、そういうものは津和野にはもう十分ある。形で何かを表現してもちょっと時間たてば飽きられるんじゃないでしょうか」

荒木氏の企みどおり、都会からきた開発室は町にしっくり馴染んでいるが、景色に融合しながらも好奇心をそそるほんの少しの異質性を孕むそのバランスは見事だ。また、鏡面の壁は外と中をすべてシャットアウトせずに足下に開口部をつくることで浮いているように見え、ちょっとした緊張感をもたせているのもおもしろい。さらに、入り口と直線上にある奥のドアをガラスにすることで、視点が突き抜け、抜けた先には緑豊かな風景が見えるように設計されている。津和野の風景と風景の間に少しだけ新しくできる空間を差し込む、これも町と建物を馴染ませるテクニックだ。「でも、実は最初に図面を見たときはあまりピンと来なくて…。元々そんなにこだわりもなくて普通の事務所のつもりだったんですよ」山越氏の言葉に、二人はちょっと苦笑い。それでも、外から不思議そうに覗いているおじいちゃん、おばあちゃんを中に案内することも多く、建物を通して町の人とコミュニケーションが生まれた。そうして町とつながることで、自分の中で津和野が特別な場所であることに気がついたという。
知恵とアイデアで立ちふさがる課題をクリア
あるものを生かしながらデザイン性も追求する
しかし、工事は決してスムーズではなかった。壁を剥がし、実測し直すと想定外の事が起こるのは改修においてよくあること。この現場も例外ではく、実際に解体してみると基礎は腐り、シロアリの被害もあった。工期が短く、費用も限られているため、頼れるのは知恵とアイデア。地元の施工会社に交渉し、安い廃材を使ってもらったり、トイレや玄関のドアは倉庫に眠っていた古い物を再利用した。「全部キレイでモダンなものを使う必要はない」長澤氏と荒木氏はそう考える。仕事をし始めて、いろいろな物がどんどん増えていけばすべてその場所に馴染んでくるはず。だからこそ、使えるものは使った方がいい。さらに、鮮やかなエンジ色に塗られた綺麗なワークスペースの上部は、ちょうど中に入れた箱の蓋をぱかっと開けたかのようなつくりになっており、古い梁と天井がそのまま残されている。天井が高く見える効果もあるが、まだ使い込まれていない真新しい空間で懐かしい顔を見たような親しみがわく。

柔軟な心で新しいことを受け入れる施主と決して妥協しない設計士が生み出したモノ。
津和野の開発室ができた後、山越氏は本社会議室の改装も二人に依頼している。木の間仕切りを斜めに配し、奥に行くほど狭くなる三角形に近い台形の空間は、奥行きが感じられ、自然光が差し込むよう設計。「最初見たときはえー!って(笑)。もっとスペースを有効に使いたいなって正直思いましたよ」 そう話す山越氏も、社員が1日8時間も過ごす場所にこうした遊び心をいれることで余裕が生まれるかもしれない、と今は考える。「この使えない空間も、決して無駄じゃないんですよね。私にはない発想でした」
二人の提案を柔軟に受け入れることで新しいものが生まれ、“イヤでイヤで仕方なかった”津和野も氏の中で特別な場所であることに気づかされた今回のコラボレーション。デザインの持つ力を感じずにはいられない。
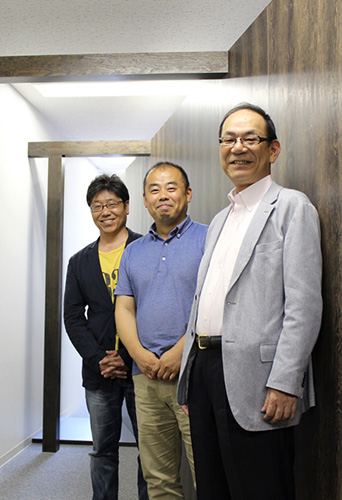
公開:2015年7月14日(火)
取材・文:和谷尚美氏(N.Plus)
取材班:清水友人氏(360)、宮窪翔一氏(design rubato)
*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。
